
2025年5月施行「戸籍の読み仮名(ふりがな)」新ルール!どう変わるの?届出方法や名前に込める愛情と、社会で生きる力について

「読み仮名」も戸籍に──名前をめぐる、新たな時代のはじまり
2025年5月26日。
この日から、戸籍法が改正され、戸籍に「氏名の読み仮名」を記載する制度が始まりました。https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
今後、出生届を提出する際には、子どもの名前の“読み”についても、自治体が確認を行うことになります。
これまでは「名前の読み仮名」は公的には記録されていなかったものの、保育園や学校、病院など、日常のあらゆる場面で必要とされてきたもの。
今回の法改正によって、「名前の読み」そのものが、より社会的な存在として正式に位置づけられることになったのです。
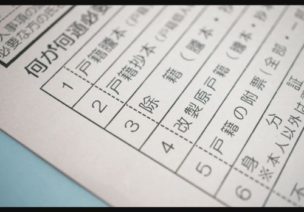
名前に込める想いと、個人の自由
「子どもにどんな名前を贈るか」──それは、親から子への最初の贈り物。
そこには、たくさんの愛情と願いが込められているものです。
どんなふうに育ってほしいか。
どんな人生を歩んでほしいか。
そんな想いを“響き”や“漢字”に託す時間は、まるで未来への手紙を綴るようなものなのかもしれません。
私自身、小さいころから人の名前に不思議と惹かれていました。
その人が持つ雰囲気や、にじみ出る個性と名前の響きや文字とのつながりに、
なんとも言えない面白さを感じていたのです。
名前を聞いただけで「ああ、この人にぴったりの名前だな」と、腑に落ちるような感覚を感じることもありました。
響きが美しい言葉、意味に奥行きのある名前に出会うたび、
「こんな素敵な名前を、いつか我が子に贈れたら」と夢見て、ノートの片隅にこっそり“赤ちゃんの名前リスト”を綴っていたものです。
テレビで耳にした名前、小説の中で出会った名前、ふとすれ違った親子の会話の中に現れた、心に残る名前……。
それらを「いつか大切な誰かに贈るために」と、宝物のように書き留めていました。
それはきっと、“誰かを深く愛する日”に向けた、私自身の静かで、心温まる準備だったのだと思います。


それでも、名前は「社会と共にある」ということ
そんな個人的な名前への想いの一方で、
1994年に起きた「悪魔くん命名騒動」は、社会に大きな衝撃を与えました。
当時の三ヶ月章法務大臣は、極端すぎる名前や一般的には読めない当て字などについて、「親の命名権の濫用にあたる場合がある」という法務省の見解を示しました。
しかし同時に、彼はこうも語っています。
「命名の基準のような価値評価がからむ事案に行政庁が一律の基準を作るのは困難だ」と。
この言葉は、名前の自由さと社会性の間で揺れる、命名の難しさを象徴しているようです。
当時、ちょうど“ステキな名前リスト”作りに夢中だった私も、このニュースには強く心を動かされました。
なんだか他人事とは思えなかったのです。
きっとその親御さんにも、何かしらの深い想いや背景があったに違いないと、子どもながらに想像しました。
ただ、その純粋な想いと、世間の価値観や一般的な印象との間に、少し距離が生まれてしまったのかもしれない……と。
名前というのは、たしかに個人の想いを込めて自由に選べるものではありますが、
同時に、社会とつながる“窓”のような役割も持っているのだと思います。
読みにくい名前、極端な当て字、あまりにもユニークすぎる響き……。
そうした名前が時に議論を呼ぶのは、「名前」が単なる個人の所有物ではなく、
“社会に開かれた存在”であるが故の繊細さを持っているからなのでしょう。
名前に込めた大切な想いが、社会の常識や価値観と意図せず衝突してしまう。
それは、名付ける側も「悪気なく、愛情を込めて選んだ」からこそ、余計に切なく、やるせない出来事なのだと思います。
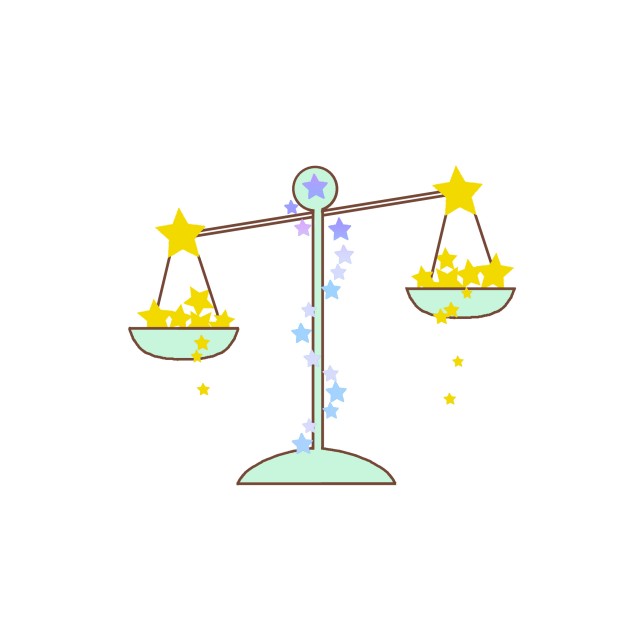
境界線を引くのは「制限」ではなく、未来への「配慮」
今回の読み仮名制度の導入も、「こうでなければならない」と厳しく縛るためではなく、
子ども自身がこれから生きていく社会の中で、名前によって不必要な困難を感じることなく、スムーズに過ごせるように──
という、ある種の「配慮」として生まれたものだと私は捉えています。
読みがまったく予測できない名前、極端な当て字、伝統的な名乗り読みの範疇を超えた自由な響きなどについては、
今後、一定の指針が示される可能性もあります。
しかしそれは、「自由の否定」を意味するのではありません。
むしろ、「名前が社会でどのように受け取られるか」という視点をそっと添え、
親の愛情深い想いと、子どもが社会で歩んでいく現実との間に、より良い橋をかけるための工夫なのだと感じます。
もちろん、時代とともに価値観は変化し続けます。
かつて“珍しい”とされた名前が、今ではごく自然に受け入れられ、同じ教室に複数人いることだって珍しくありません。
最終的に最も大切なのは、その名前に込められた親の温かい願いと、
子ども自身が成長したときに「この名前でよかった」「自分の名前が好きだ」と心から思えること、なのです。

【知っておきたい】出生届の提出と「読み仮名」のポイント
さて、大切なお子さまが誕生し、素敵な名前が決まったら、次に行うのが「出生届」の提出です。
新しいルールも踏まえつつ、基本的なポイントを簡単にご紹介しますね。
- いつまでに?
生まれた日を含めて14日以内に届け出る必要があります。 - どこへ?
お子さんの本籍地、届出人の所在地(お住まいの場所)、または赤ちゃんが生まれた場所の市区町村役場です。 - 誰が?
原則として、お父さんまたはお母さんです。 - 何を持っていくの?(主なもの)
- 出生証明書(通常、出産した病院や助産院でいただけます)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- (自治体によって、その他必要なものがある場合も)
- 「名前の読み仮名」も忘れずに!
今回の法改正で、戸籍に「氏名の読み仮名」を記載することになりました。
出生届にも読み仮名を記入する欄がありますので、事前にしっかり決めておきましょう。
大切なこと:
必要な持ち物や手続きの詳細は、届け出る市区町村役場によって異なる場合があります。
事前にホームページで確認したり、電話で問い合わせたりしておくと安心ですね。
最後に―「名前」は、人生で最初の、そして最高の贈り物
名前は、生まれて最初に贈られる“人生の名刺”。
たったひとつの音に、たった一文字に、
名付ける人の深い愛や、子の幸せを願う祈りが宿っています。
日本のそんな優しく温かい命名の文化を、私たちはこれからも大切に育んでいきたいですね。
だからこそ、自由な発想を大切にしながらも、その名前が社会の中でどう響くかという視点も少しだけ持って。
そして何よりも、子ども自身が成長したときに「自分の名前が大好き!」と心から思えるような、そんな名前を贈れたら本当に素敵です。
今回の法改正が、一人ひとりが「名前」の持つ意味や大切さについて、改めて深く考える素晴らしい機会になることでしょう。
そのことを、私は心から嬉しく思っています。
赤ちゃんとの新しい生活が、たくさんの愛と喜びに満ちたものになりますように。
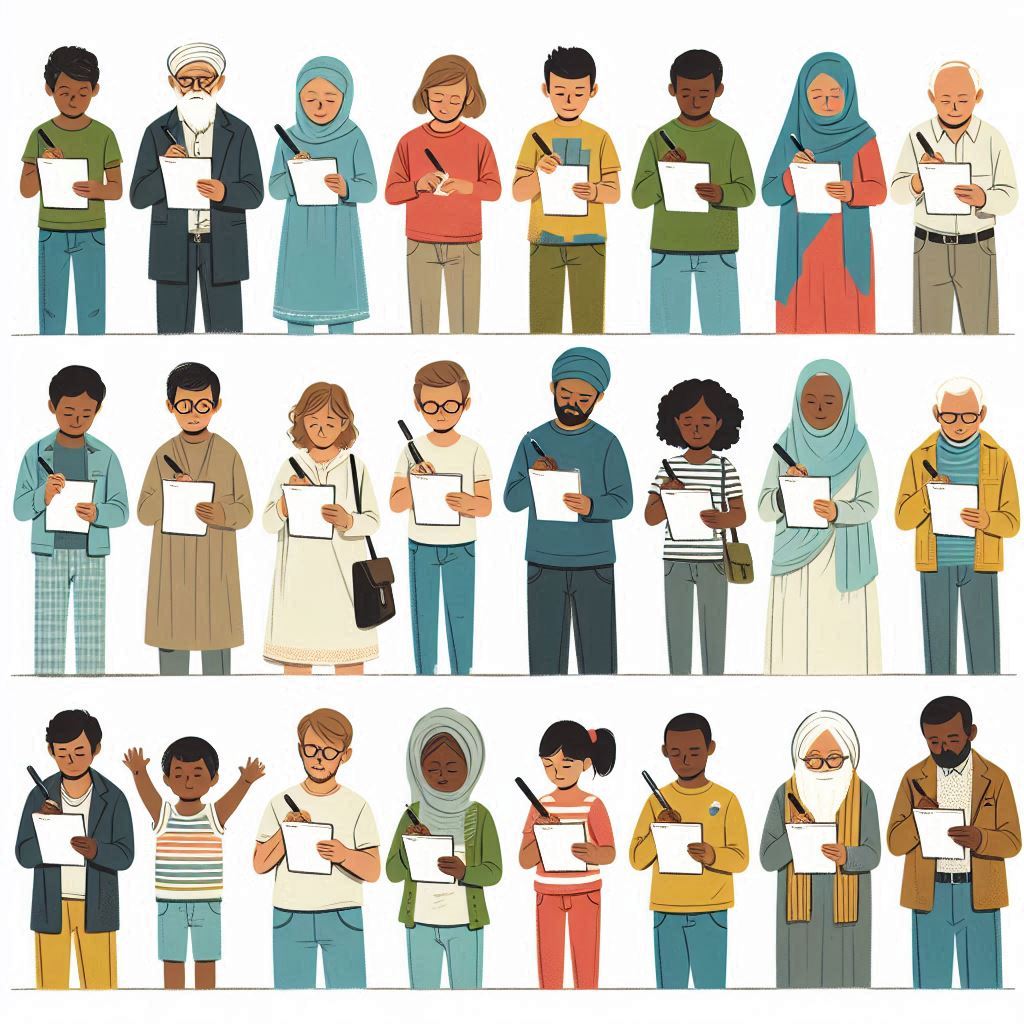
-

60年に一度の「丙午」到来。この激動を“追い風”に変える、たった3つのお名前アクション
-



【2026年大寒】大寒卵はいつ食べる?お名前鑑定士が教える金運アップする「最強の食べ方」と入手方法まとめ
-



【お客様の声】1月限定・新年スペシャル鑑定2026のご感想と、現実を動かす小さな一歩!「ようやく心が定まりました」
-



【2026年最新情報】あかちゃんの命名・名前ランキングTop5徹底解説!後悔しない名付け方や名前診断、命名無料相談について
-



【2025年12月コールドムーン】今年最後の満月が告げるメッセージとは?2026年飛躍のための開運行動も
-



祝【2025年紅白初出場!】M!LK(ミルク)のメンバーやグループ名の由来は?姓名判断とカタカムナで紐解く最強運勢
![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)











コメント